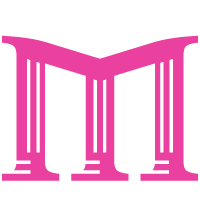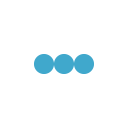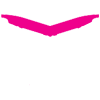- 0318 Museum
- 173F 肖像神話 タマラ・ド・レンピッカ
- 肖像神話 タマラ・ド・レンピッカ 続き #1
肖像神話 タマラ・ド・レンピッカ 続き #1
1920年代、ベル・エポックのパリ。
最新のブガッティから鋼鉄のような目がこちらを睥睨する。
およそメカニックな冷たい画面から誘惑的な官能が匂い立つのは、
ぬめりとした光沢のせいだろうか。
レンピッカの絵には人を寄せ付けない尊大さがあり、それは彼女の人柄そのものでもあった。
若く美しい新進の女流画家レンピッカ。
彼女のパーティにはパリ選りすぐりの上流階級の面々が揃い、翌日の新聞にはそのようすが仰々しく報じられた。
富、栄誉、美貌、それらすべてを彼女は完璧に備えていた。
その数年前、
彼女が夫と共に革命の嵐吹き荒れるロシアから亡命した時、彼らは一文無しだった。
頼りにならない夫。
惨めさのどん底で、彼女のしたたかに生きる力は爆発する。
そうだ、子供の頃得意だった絵で身を立てよう。
ロシアでの贅沢な生活で磨かれたセンスは、この時期のブルジョアの趣味によく合った。
レンピッカに絵筆を動かさせ続けたものは、お金と栄誉への飢餓感だった。
そんなタマラだが、 娘のキゼットだけをモデルに子供の肖像画のシリーズを描き続けた。
最後の画像は『ピンクの服を着たキゼット』(1926年)