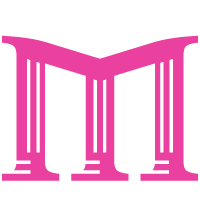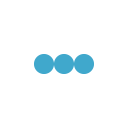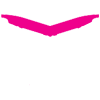【手彫証券印紙】第五次発行1銭黒:用紙について
初版 2022/12/17 06:23
改訂 2023/10/28 06:37
はじめに
このLabログでは第五次発行1銭黒色印紙で使われた用紙について解説します。
用紙と目打は明治初期の切手や印紙を収集する上で最もややこしい分野で、当時は技術革新が急激に進んでいたために、切手/印紙の印刷技術の進歩もめぐるましく、時代に応じて様々な用紙と目打が使われていました。これからご紹介する第五次発行1銭黒色印紙でも数種類の用紙が使われていて、カタログでの大分類だけでは収まらないヴァリエーションがあって、興味が尽きません。
【2022/12/18 各用紙の拡大画像を追加しました】
第五次発行1銭黒色印紙の用紙
第五次発行1銭黒色印紙では洋紙が使われており、カタログではポーラス紙と無地洋紙の2種類が挙げられてますが、もう一種類、"brown wove paper"と呼ばれる茶色い洋紙が長谷川(2022)によって紹介されています。
最もよく見かけるのはポーラス紙と呼ばれるやや厚手の洋紙で、紙質が完全に均一ではなく、どこかボサッとした印象を受ける紙です。ただし、同じポーラス紙でも「ポーラス」=「多孔質の」という名前のとおりに所々で孔が透けて見えて、裏面にまでインクが滲んでいるものと、明確な構造はないが(後述する)紙にインクが若干滲んでいるというものまで幅があるように見受けられます。
一番わかりやすいのは白っぽくて厚手の紙で、刷色が濃い黒色のものでしょう。表面はインクが滲み気味で細かい線の輪郭がぼやけていたり、細かい文様(特に飾り文様の飾り毛)が潰れてしまっている印象を受けます。

裏面は、印面がわかるくらいインクが滲みでていて、均一に滲んでるというよりも所々からインクが裏面まで点状に滲み出ているという印象を受けます。また、目打山の先端(目打がちぎれたあと)に細かい繊維がボサボサっとはみ出ているのもこの用紙の特徴です。

同じ白っぽいポーラス紙で、多孔質であるという構造がよりはっきりとわかるものもあります。これは画像処理で構造を強調したものですが、小さな孔がたくさんあるように見えるのがわかるでしょうか。特に下のマージン部分では小さな孔が規則正しく並んでいるのがわかります。別種の紙として扱えるのかどうかはっきりしておらず、手彫切手や旧小判切手の洋紙との対比で詳しく調べる必要があると考えています。

【2022/12/17追加】構造がはっきりと見えるポーラス紙の、耳紙の部分の拡大写真です。全体的にムラがあって、所々に孔が空いているのがわかります(→ホットケーキを焼いているときの、裏返す前に穴がプツプツとあいてきた感じに似ていますね)

【2022/12/19 追記】この用紙の中央部の拡大画像です。菊紋の8番目小花弁(重弁)が欠落しているので、Plate I, Pos.20ですね。繊維が荒くて長さもまちまち(どちらかというと長め)なので表面の均一性が悪く、凸凹してて、インクの乗りが妨げられたり、滲んだりしているのがわかります。

一方で、白さがあまり感じられない、藁色がかった厚手の紙もあります。構造も規則的なものはないのですが、全体的に不均一な感じを受けるもので、目打の切れ味が劣っていてボサッとした切れ方になっています。印刷効果も芳しくありません。明らかに(次に説明する)無地洋紙ではないのでポーラス紙として整理していますが、明らかに別物という気がしてなりません。(旧小判切手でいう初期普通紙の無地紙に近いのでしょうか?)


画像処理して構造を強調したものです。先に示したポーラス紙と比べると明確な構造のパターンがなく、全体としてムラがあるという感じが見受けられます。このように見た目も紙質も違いがあるので、白っぽいポーラス紙とは区別して“厚手無地粗紙”とでも呼ぶのが良いような気もしていますが、こちらも同時期の切手の用紙との関連性をもっと勉強する必要があると感じています。

【2022/12/19 追記】この用紙の特徴的なボロボロ感がよくわかる、耳紙の目打穴付近の拡大画像です。目打穴の抜けが悪く、また、目打をちぎったところが毛羽立っているのがわかります。

これらの紙に対して、「無地洋紙」は文字どおり梳き模様などの構造がない均一な洋紙で、ポーラス紙に比べると印刷の仕上がりが格段に良く、細かい印刻までくっきりはっきりしているのが特徴です。色は若干茶色味を帯びていて、表面は滑らかで、目打山からの細かい繊維も少なめで、スッキリとした印象を受けます。

画像処理をしても明確な構造は確認できません。均一性の高い紙であることがわかります。

【2022/12/17追加】無地紙の耳紙の部分の拡大写真です。先に示したポーラス紙や厚手のとは違ってムラがなく、孔もあいていません。目打穴も綺麗に抜けています。

さて、この無地洋紙のヴァリエーションとでも言うべき、茶色味の濃い平滑な洋紙があります。こちらの第五次発行1銭黒印紙1枚貼り証書、明治14年の使用例をご覧ください。

銀行の手形の裏面を受取証書として使ったもので、受取証書なので金高に関わらず印紙税一銭というありふれたものですが、使われている印紙は全体的に茶色がかった無地紙に印刷されており、ファーストインプレッションは普通の無地紙と異なる雰囲気です。
この証書そのものが結構変色しているので、単なる日焼けか裏糊の経年劣化による変色かなと思ったのですが、日焼けによるものとしても、裏糊の経年変化で用紙が変色したとしても、あまりにも均一に変色していて、どちらにせよ不自然な気がいたします。
この証書と合わせて入手した他の数枚の証書に貼られている第五次発行1銭黒印紙も同じような色調の紙に印刷されていました。なので、全ての印紙が同じように変色したという可能性も低そうです。また、別の明治14年の証書に貼られている無地洋紙の1銭印紙も、用紙の色が明らかに同じような茶色味を帯びています。

さらに単片でも同じような雰囲気の茶色がかった無地紙に印刷されているものがあって、色調も様々なものがあります。右の印紙のように、中には茶色がかなり強いものもあって、今のところは用紙そのものがこのような色調であった可能性を信じて別扱いとしています。

【2022/12/18追記】この茶色無地紙のクローズアップ写真です。色味が違う2枚の印紙の、中心部の拡大画像を並べてみました。普通の無地紙と比べると繊維が短くて密に詰まってて、フェルトのような印象です。構造は全く見えません。


この茶色味がかった無地紙の特徴はなんといっても印刷効果が抜群に優れているところでしょう。ポーラス紙に印刷された滲んだようなぼやけたインプレッションとは全く異なっていて、拡大図のように、細かい線までくっきりと印刷されています。普通の無地紙よりもクッキリしたインプレッションです。上の拡大画像でもわかるように、繊維が細かくて密に詰まっているので、インクの滲みの原因になる用紙表面の凸凹がほとんどなく、インクの境界がクッキリとしています。

この用紙、長谷川氏の大著(2022)で「brown wove paper」として紹介されているものと同じと考えて、今のところは「茶色無地紙」(仮称)と名付けて整理していますが、果たしてどうなのでしょうか。出現時期や目打との関連があるのか否か、マテリアルが不十分でまだよく理解できていません。
「駄物」の第五次発行1銭黒印紙といえど、用紙一つとってもまだまだ楽しめる要素が残されているようです。