慈雲尊者ゆかりの寺
初版 2020/06/11 23:07
改訂 2020/06/11 23:07
1.河内・野中寺
授戒の地
〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上5丁目9−24
→西国四十九薬師霊場ほか札所

西国薬師14番 野中寺
https://muuseo.com/Satory/items/781
 法見
法見2.法楽寺
得度の地
〒546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目18−30
→近畿不動尊、大阪十三仏、摂津八十八所ほか札所

摂津40番 法楽寺
https://muuseo.com/Satory/items/47
 法見
法見3.信州・正安寺
参禅の地
尊者が法楽寺住職を辞して法弟松林に譲り、3年間弱参禅した禅宗寺院。曹洞宗末寺。当時の堂塔は、寛政七年(1795)の火災によって焼失して無い。
〒385-0031 長野県佐久市内山7864
4.河内高井田・長栄寺
正法律宣揚の地
尊者の晩年に至るまで、教化布教活動の中心的場所
〒577-0054 大阪府東大阪市高井田元町1丁目11−1
→新真言宗、河内西国札所

河内西国33番 長栄寺
https://muuseo.com/Satory/items/84
 法見
法見5.有馬・桂林寺(廃寺)
「方服図儀」著述の地
現正福寺(しょうふくじ)。尊者当時の本堂、釣鐘、桂林寺寺門瓦が残る。
→跡地に正福寺が移転
〒651-1504 兵庫県神戸市北区道場町平田862
6.河内・不動寺(廃寺)
→跡地に重願寺が移転
〒579-8022 大阪府東大阪市山手町12−3
→大阪三十三所札所

大阪三十三所観音霊場(満願不可能)
https://muuseo.com/Satory/collection_rooms/45
 法見
法見7.京都阿弥陀寺(廃寺)
京都の信徒の懇請によって入寺され、さかんに十善の法を説かれて『十善法語』を著された。尊者遷化は文化元年(1804)。春秋八十七。
→跡地が京和幼稚園となっている
〒602-8366 京都府京都市上京区 行衛町439−2
阿弥陀寺は北野天満宮の供御所七保のうちの一つ,六の保の社。
寛保3(1743)年に殊尊院と改称したが,明治15(1882)年頃廃寺
8.河内・高貴寺
正法律の拠点
尊者当時の僧坊が現存。
尊者像、縄牀(じょうしょう)等、尊者の遺品が数多く残されており、中でも『梵学津梁(ぼんがくしんりょう)』一千巻は世界のサンスクリット研究者の注目を集めるところ。奥の院大師堂の側に尊者の墓地がある。
〒585-0013 大阪府南河内郡河南町大字平石539
→河内西国札所

高貴寺
https://muuseo.com/Satory/items/1060
 法見
法見https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E9%9B%B2
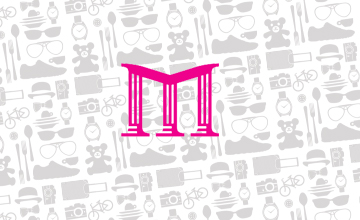
慈雲 - Wikipedia
大坂中之島(現在の大阪市北区)の高松藩蔵屋敷で上月安範の子として生まれ、父の遺言により13歳の時に摂津の法楽寺(大阪市東住吉区)で出家、同寺の住職・忍網貞紀に密教と梵語(サンスクリット)を学ぶ。18歳の時に、忍綱の命で京都に行き、伊藤東涯に古学派の儒学を学ぶ。翌年に奈良に遊学し、顕教、密教、神道と宗派を問わず学び、河内の野中寺(羽曳野市)で秀厳の教えを受けて、戒律の研究を始め、1738年(元文3年)、具足戒を受けた。翌年には忍網から灌頂を受け、法楽寺の住職となったが、2年後に住職を同門に譲った。その後、信濃に曹洞宗の僧侶の大梅を訪ね、禅も修行した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E9%9B%B2
#比較
#参考

法見
西国三十三ヶ所を基調にそこから派生した観音霊場を周り願掛けのため千観音を目指してちょこちょこ神社仏閣をお参りしております。朱印集めが面白く無節操に集めてはいましたが思い直して
限定や特別な朱印は減らす方向で考えているので少なめです。
定期的に座禅などして自分を律しながら、日々ほどほどに生活しております。
モノグサ、ナマグサではありますが一応、三帰依、五戒、十善戒を受けて戒名・法名「法見」を賜っていますので、仏教的な活動はこちらを名乗ります。
22人がフォロー中
-
Items
1,586
-
Lab Logs
49
-
Likes
744
Since September 2019





